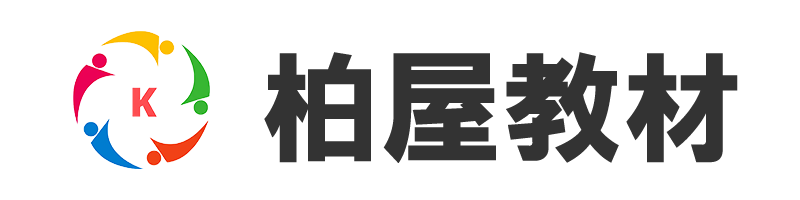毎日暑いですね~!
米沢市では、先日、観測史上最高の38.4度を記録しました。
山形県内は引き続き厳しい暑さ続くようです。熱中症にも気を付けていきたいところですね。
さて今回は、総合初等教育研究所参与の北俊夫先生が示唆された内容をもとに、
「図書離れをどうくい止めるか」について考えてみたいと思います。
■ 子どもたちの「図書離れ」が進んでいる現状
北先生によると、現在の子どもたちや若者の間で「図書離れ」「不読率の上昇」が深刻化しているそうです。
高校生や大学生の多くが、1か月に1冊も本を読まないというデータもあります。
一方、小学生は「朝読書」など学校での読書活動があるため、比較的読書習慣が維持されているものの、個人差が大きいという課題も。
背景には、
- 書店の減少で身近に本と出会う機会が減っている
- 情報収集の手段が、テレビやインターネットに移行している
といった社会的な変化があるといわれています。
■ 読書が子どもたちの力を育む
北先生は、「読書には一人一人の想像力や創造性を養い、理解力や表現力を伸ばす力がある」とおっしゃっています。
映像メディアでは得にくい、じっくり考える力や文字への親しみは、子どもの成長に欠かせません。
だからこそ、「学校教育の中で、本を“人生の伴侶”にできるような読書体験を積ませることが重要」と北先生は強調されています。
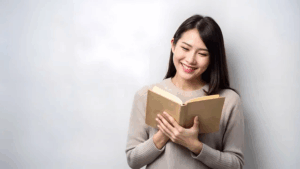
■ あらゆる教科で図書館を活用する
学校図書館の利用というと、国語科の「読書の時間」を連想しがちです。
しかし北先生は、「国語以外の教科でも図書館を活用することが大切」と述べています。
例えば…
社会や理科で調べ学習の一環として関連書籍を探す
総合学習の時間で資料収集の場として利用する
ある学校では、単元に合わせた図書を図書館から廊下や教室に持ち出し、「学年文庫」として配置しているそうです。
必要なときに、必要な本が手に取れる環境を整える工夫ですね。
■ 学校図書館の位置づけを見直す
校舎の端にあって、施錠されがちな図書館では、子どもたちの足が遠のきます。
北先生は、「子どもたちが気軽に立ち寄れる場所に図書館を配置し、日常的に開放することが理想」とおっしゃいます。
図書館主任の先生方を中心に、「子どもの立場で使いやすい運営」を検討してみるのも良いかもしれません。
■ 作品コンクールへの積極的な参加を
読書感想文や作文、絵画、新聞づくりなど、作品コンクールへの応募も
子どもたちの表現力や構成力を伸ばす機会です。
近年は応募数が減っているそうですが、
北先生は「第三者から評価を受けることは、子どもたちの自信や励みにつながる」と語ります。
学級・学年で紹介し、関心を持たせることが大切です。
先生方へのお願い
北先生の言葉をお借りすると、「学校教育の中で本に触れる場面を増やすことが、図書離れを防ぐ鍵」です。
弊社としても、学校教材販売の立場から、先生方の図書館活用や読書活動の取り組みを応援してまいります。
「学年文庫を作りたい」「関連書籍を探している」などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
子どもたちに、読書の楽しさと力を届けるために📚
学校・先生・地域で一緒に工夫していけたらと思います。